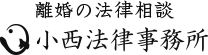医者・医師・歯科医師を夫にもつ妻の離婚について ~私立大学医学部に通う原審申立人が、父である原審相手方に対し、現在の養育費では学費等に不足が生じているとして扶養料の支払を求めた事案において、原審相手方は養育費のほかに一定の扶養料を分担する義務を負うべきとしたうえで、扶養料の分担額について、分担対象、分担割合、分担額から控除すべき額等を認定し、分担すべき扶養料を算定して支払を命じた事例~
- 医者・医師・歯科医師
目 次 [close]
医学部に通う子が離婚した父に対し、扶養料の支払いを求めた事案
本件は、23歳の医学部生である子(原審申立人)が、父(原審相手方)に対し、離婚時に父と母が取り決めを行った養育費では、医学部の学費が不足しているとして、扶養料の請求をした事例です。
父母が離婚の際に養育費の取り決めを行っていたとしても、子が要扶養状態にあるのであれば、子は、子自身が申立人となって、扶養義務者に扶養料を請求することができますが、この場合、父母間で先に定められた養育費との関係が問題となります。
前提として、父と母は、離婚時に、子の養育費として、子1人あたり500万円の一時金と、子らが大学(医学部を含む)卒業まで1人あたり月額25万円の支払いをするほか、子が私立大学の医学部に進学する場合は、子が直接父に希望を伝えて、不足する養育費については、別途協議するとの取り決めがなされました。
また、財産分与として、父が住宅ローンを組み5000万円で購入したマンションの持ち分2分の1を母に分与し、父にて住宅ローンを完済し、将来、父の持分2分の1も全て母に譲渡するものとされていました。
大阪高裁平成29年12月15日決定の判断
1 父の扶養料分担義務について
「ア 原審相手方は、母への離婚申入れ当時(平成22年)から、原審申立人が医学部を含めて大学を卒業するまで原審申立人を扶養する義務を引き受ける旨伝え、本件離婚時(平成24年)にも、養育費支払義務の終期を原審申立人の医学部を含む大学卒業までとすることを了承している。
したがって、原審相手方は、原審申立人の大学在学中、母とともに、原審申立人の扶養義務を負う。
イ また、原審相手方は、母への離婚申入れ当時(原審申立人15歳)から、月々支払う養育費には学費を含んでいるが、原審申立人が私立大学の医学部に進学した場合に養育費とは別に大学在学中の費用をできるだけ負担する旨申し出ている。
そして、原審相手方の属性をみると、父親が医師で、自らも医師として稼働し、本件離婚時点には、開業医として高額な収入を得ており、その状況に変わりはない。
その上、原審相手方は、原審申立人から、高校卒業後の進路について相談を受けた際、医学部への進学も考えている旨聞かされて賛同する意向を示しており、その間、原審申立人が私立大学の医学部へ進学することを否定する旨明言した形跡はない。
そのような中で、原審相手方は、原審申立人が私立高校3年生で大学受験を控えていた本件離婚時に、子らの養育費(1人当たり月額25万円)の支払とは別に、私立大学の医学部に進学する場合を想定した本件協議条項に合意しているのである。
以上のとおりの本件協議条項の文言に加え、本件協議条項を合意するに至った経緯、原審相手方の属性、原審申立人の進路等に関する原審相手方の意向等を総合考慮すれば、原審相手方は、本件離婚当時、原審申立人が私立大学医学部への進学を希望すればその希望に沿いたいとし、その場合、養育費のみでは学費等を賄えない事態が生じることを想定し、原審申立人からの申し出により一定の追加費用を負担をする意向を有していたと認めるのが相当である。
ウ 原審相手方は、原審申立人が奨学金を受ければよい、原審申立人にはアルバイト収入や貯蓄がある、原審申立人が複数のサークルで活動する余裕があるなどと主張する。
しかし、原審申立人が本件医学部に進学したことで、本件離婚の際に合意された養育費(一時金を含む。)では私立大学の医学部の学費等を賄えないという本件協議条項の想定した事態が現に生じている。
したがって、原審申立人が原審相手方に対して本件協議条項に基づき追加の費用負担を求めている以上、原審相手方は、これに従い、上記の養育費のほかに一定の扶養料を分担する義務を負うというべきである。
原審相手方の主張は採用できない。」
として、父の扶養料分担義務を認める旨の判断をしました。
2扶養料分担義務の始期
「原審申立人が本件協議条項に従って原審相手方に協議を申し入れた(平成27年■月頃)のは本件医学部への進学から約半年後であり、本件申立て(平成28年■月)は本件医学部進学から約1年4か月後である。
しかし、原審相手方は、本件離婚後7か月で再婚すると、子らとの交流に応じなくなり、再婚から9か月後には子らの養育費の減額を求める調停を申し立て、子らとの連絡を拒否するようになった。
さらに、原審相手方は、一浪中の原審申立人から私立大学に進学することになった場合の援助の申し出を受けても、こっちにはこっちの事情があると述べて突き放し、本件医学部進学後の平成27年■月に原審申立人から手紙で面会の申入れを受けるなどしても、面会に応じないどころか、今後一切連絡してこないようにと応答した。
このように、原審申立人が原審相手方に本件医学部の学費等についての協議を申し入れることができずにいた原因は、上記の原審相手方の対応にあるといえる。
そうすると、原審申立人が原審相手方に対して本件医学部への進学後(平成27年■月)速やかに学費等について原審相手方と協議しなかったとしても、扶養料分担義務の始期を同月より後らせるべきではない。
したがって、その始期については、本件医学部進学の月である平成27年■月とするのが相当である。」
として、父の扶養料分担義務の始期について、医学部進学のとき、と判断しました。
3 扶養料分担額の算定
「ア 分担対象
(ア) 本件においては、本件離婚当時、原審申立人の養育費(月額25万円)とそれ以外の私立大学医学部へ進学した場合の追加費用とが別に取り決められている。
そして、平成27年■月には、原審相手方の申立てに係る養育費減額請求事件の中で、上記養育費の額が標準的算定方式に基づいて改めて検討され、その額が標準的算定方式に従って算定される額を下回るものではないとの決定が確定している。
そうすると、本件においては、養育費のうち、私立大学の医学部の学費等標準的算定方式によって算定される額では賄えない部分のみを扶養料として原審相手方及び母がその状況に応じて分担し合うこととするのが相当である。
他方、原審申立人の日々の生活費を含む標準的算定方式で考慮されている費用については、本件の扶養料の算定に当たって考慮すべきものに含まれないことになる。
(イ) ところで、原審相手方の平成28年の収入は、給与収入が587万6620円、事業所得が4851万1327円、雑所得が66万7133円である。
そのうち、給与収入587万6620円を標準的算定表の自営収入に換算すると約430万円となり、また、事業所得4851万1327円及び雑所得66万7133円の合算額から、社会保険料211万0150円を控除した上で、現実に支出されていない費用と考えられる青色申告特別控除額65万円及び専従者給与900万円(原審相手方の妻は実質的には専業主婦である。)を加算すると、5671万8310円となる。
そうすると、原審相手方の総収入は、自営収入6101万8310円と同等とみることができる(430万円+5671万8310円)が、この金額は、標準的算定表の自営収入の上限(1409万円)の4倍以上に上る。
そして、標準的算定方式によって算定される養育費は、公立学校の教育費相当額(年間33万円程度)を含んでいるが、本件のように、義務者の収入が公立学校の子のいる世帯の平均収入を大きく上回る場合には、結果として、公立学校の教育費以上の額が相当程度考慮されていることになる。
実際、標準的算定表のいずれによっても、子2人での月額合計の上限額が30万円ないし36万円であって、子1人当たりの養育費の上限が月額25万円を下回っている。
これらの事情に照らせば、現時点での原審申立人の養育費1人当たり月額25万円の中には、私立学校に係る費用の一部も一定程度考慮された額も含まれているとみることができる。
(ウ) さらに、本件では、原審申立人及び母は、本件マンションに居住しているところ、本件マンションは、原審相手方が母との別居後に、離婚後の母及び子らの住居として、5000万円の住宅ローンを組んで購入したものである。
そして、原審相手方が本件離婚時にその持分2分の1を母に財産分与として譲渡し、その余の原審相手方の共有持分を将来原審申立人に譲渡することを約束する一方、そのローン全額を原審相手方において完済しているため、現在、原審申立人及び母は、母による管理費等の負担のみで本件マンションに居住できている(原審申立人は、将来本件医学部付近で一人暮らしをする可能性を主張するが、本件マンションと本件医学部との距離等に照らし、転居しなければならない事情は見い出しがたい。原審申立人の上記主張は採用できない。)。
(エ) 上記(ア)ないし(ウ)の事情を考慮すれば、本件において原審相手方と母とが分担し合う扶養料は、学納金3141万円のほか会費等を含めた額である約3200万円から公立学校の教育費相当額約200万円(年額33万円程度の6年分)を控除した3000万円に止めるのが相当である。したがって、その余の教育費、医療費等も本件の扶養料分担の対象とすべきである旨の原審申立人の主張は採用できない。
イ 分担割合
原審相手方は、医師として長年稼働し、平成21年■月に整形外科医院を開業し、その後8年以上高額の収入を得てきた。
他方、母は、元々薬剤師の資格を有しており、原審申立人が本件医学部進学後、薬剤師としてパートでの稼働を再開し、平成28年■月以降は正社員に稼働形態を変えている。
その結果、母の収入は年収650万円程度となっている((526万5125円-39万2000円)÷9月×12月)。
このような原審相手方と母の収入に加え、原審申立人及び母が母による管理費等の負担のみで本件マンションに居住できているといった両名の生活状況等を考慮すると、原審相手方と母の分担割合については、4対1とするのが相当である。
ウ 原審相手方の分担額から控除すべき額
(ア) 母は、本件離婚時の合意により、本件離婚後の原審申立人の月々の養育費に加えて、本件離婚時に同人の養育費の一時金500万円を受け取っているが、これは、大学受験を控えた原審申立人の学費等に充てられるべきものである。
(イ) また、原審相手方は、原審申立人が高校卒業から大学入学までの2年間の浪人中も、原審申立人の養育費を支払っているが、原審申立人が大学進学のために二浪することまでは納得していなかったといえる。
このことを考慮して、浪人2年目の分の原審申立人の養育費300万円(月額25万円の12か月分)については、原審相手方の分担額から控除することとする。
(ウ) さらに、本件では、原審申立人の養育費の月額25万円が子2人の月額合計の上限額(標準的算定表によれば1人当たり月額18万円)を上回っており、上記養育費の額には、私立大学に係る費用の一部も一定程度考慮されていること(前記ア(イ))をも考慮すれば、本件医学部在学中の6年間、月額10万円程度の合計720万円(10万円×12か月×6年)を控除するのが相当である。
(エ) 以上によれば、原審相手方の分担額から控除すべき額は、1520万円となる。
(計算式 500万円+300万円+720万円=1520万円)
エ 扶養料の額
上記アないしウの検討結果からすれば、原審相手方が分担すべき扶養料の額は、年額150万円となる。
(計算式 3000万円×0.8=2400万円
2400万円-1520万円=880万円
880万円÷6年≒150万円)」
と判断しました。
4 扶養料の支払方法及び時期
「本件医学部の学納金等の納付時期及び額は、分割の場合、第1期(3月)が年額の半分程度、第2期(8月)及び第3期(12月)がほぼ同額(年額の約4分の1程度)となっている。
そうすると、扶養料(年額150万円)の支払方法は分割とし、その時期は各納付月の前月とし、その額は各納付の比率に合わせることが相当であり、具体的には、当該年度開始(4月)の直前の2月末日限り80万円、同年7月末日及び同年11月末日限り各35万円とする。」
と判断しました。
5 まとめ
そして、本決定は、最終的に、
「以上のとおりであるから、原審相手方は、原審申立人に対し、平成27年度ないし平成29年度の3年間の未払いの扶養料合計450万円(150万円×3年)と平成30年2月から平成32年11月まで、毎年2月末日限り80万円並びに毎年7月及び11月の各末日限りそれぞれ35万円を支払う義務を負う。
よって、上記判断に抵触する限度で原審判を変更することとし、主文のとおり決定する。」
と判断し、父の扶養料を上記のようなかたちで支払うべきことを認めました。
- 2020.03.04
「医者・医師・歯科医師」の夫との離婚問題なら小西法律事務所へ - 2019.04.15
医者・医師・歯科医師の夫をもつ妻の離婚について ~医療法人の債務を連帯保証している場合の財産分与〜 - 2019.04.08
医者・医師・歯科医師を夫にもつ妻の離婚について ~保険と将来の退職金~