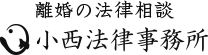財産分与とは?離婚前に知っておくべき基礎知識
- 財産分与
離婚を考えるとき、お金の問題は避けて通れません。その中でも特に重要な問題は、「財産分与」です。財産分与とは、夫婦が結婚生活の中で協力して築き上げた財産を、離婚の際に公平に分け合う手続きのことです。財産分与は、離婚後の新しい生活を始めるための大切な基盤となります。このコラムでは、清算的財産分与について、対象となる財産、手続きの流れ、手続を進める上での注意点など、離婚前に知っておくべきポイントをわかりやすく解説します。
目 次 [close]
財産分与の基本
まず、財産分与の基本的な考え方について見ていきましょう。いつからいつまでの財産が対象になるのか、財産の名義は関係あるのか、夫婦の貢献度はどのように評価されるのか、という3つのポイントが重要です。
対象期間:いつからいつまでに得た財産が対象?
財産分与の対象となるのは、婚姻期間中に夫婦が協力して築いた財産です。一般的には、婚姻した時点(または同居を開始した時点のいずれか遅い方)から、離婚する時点(または別居を開始した時点のいずれか早い方)までに形成された財産が対象となります。したがって、夫婦の協力関係がなくなったといえる別居期間中にそれぞれが築いた財産は、原則として財産分与の対象外です。なお、ケースによっては、同居中に形成された財産であっても、夫婦の経済的な協力関係が解消されているような事情があれば、財産分与の対象財産とならないと評価される場合もあります。
名義の考え方
財産の名義が夫婦のどちらか一方になっていても、それが婚姻期間中に夫婦が協力して得た財産であれば、財産分与の対象となります。例えば、夫名義の預金口座内の預金や不動産であっても、それが夫婦の協力によって得られたものであれば、当該財産について、妻も分与を請求できます。どちらのものかハッキリしない財産についても、夫婦の共有財産と推定されます。
夫婦の貢献の評価
財産を分ける割合は、財産形成に対する夫婦それぞれの貢献度(寄与度)によって決まります。実務上は、**夫婦の貢献度は平等であると考えられ、原則として「2分の1ずつ」**とする、いわゆる「2分の1ルール」が広く採用されています。これは、例えば一方が専業主婦(主夫)として家事や育児を担い、もう一方が外で働いて収入を得ていた場合でも、家庭を支える内助の功が財産形成に貢献したと評価されるためです。ただし、夫婦の貢献度に大きな差がある特別な事情がある場合は、この割合が柔軟に変更されることもあります。
対象になる財産
次に、具体的にどのようなものが財産分与の対象財産となるのかを見ていきましょう。
預貯金・現金
婚姻期間中に夫婦で協力して貯めた預貯金や、家庭内に保管していた現金(いわゆるタンス預金)は、どちらの名義であるかを問わず、財産分与の対象となります。
不動産・車など
婚姻期間中に購入した土地、建物、マンションといった不動産や、自動車などの動産も財産分与の対象です。これらも名義は問いません。不動産や車は、そのままどちらかが取得し、その評価額に応じて相手に代償金を支払う方法や、売却して現金を分ける方法などがあります。
保険・退職金の扱い
将来受け取る可能性のある財産も、財産分与の対象に含まれることがあります。
- 保険: 婚姻期間中に支払った保険料に対応する、別居時点での解約返戻金が財産分与の対象となります。
- 退職金: 別居時点ですでに退職金が支払われている場合はもちろん、将来支払われる予定の退職金も、婚姻期間(同居期間)に対応する部分については財産分与の対象となるのが一般的です。
対象外になる財産
夫婦の協力とは無関係に得た財産は「特有財産」と呼ばれ、原則として財産分与の対象にはなりません。
独身時の貯金
結婚する前からそれぞれが持っていた預貯金や財産は、特有財産にあたります。例えば、独身時代に貯めた預金や、その預金で購入したものは、離婚時の財産分与の対象外です。
贈与・相続で得た財産
婚姻期間中であっても、親や親族から相続した遺産や、贈与によって得た財産は、夫婦の協力によって築いたものとはいえないため、特有財産として扱われます。したがって、原則として財産分与の対象にはなりません。
特有財産のその他の例
上記以外にも、特有財産とみなされるものがあります。例えば、不法行為の被害に遭った際に受け取った慰謝料など、個人的な事情に基づいて得た金銭は、夫婦の協力によって得た財産ではないため、特有財産として財産分与の対象から外れます。
手続きの流れ
財産分与は、まず夫婦間の話し合い(協議)から始めるのが一般的です。話し合いで合意できない場合は、家庭裁判所の手続きを利用することになります。
離婚協議の進め方
離婚協議では、財産分与を行うにあたって、お互いがどのような財産を持っているかをリストアップし、それぞれの財産をどのように評価するかを決めます。その上で、分与の割合(通常は2分の1)に基づいて、具体的に誰がどの財産を取得し、必要であれば差額をどのように清算するかなどを話し合います。離婚後の生活設計も見据えながら、現実的な落としどころを探ることが大切です。
調停申立てのポイント
夫婦間の話し合いで合意に至らない場合や、そもそも話し合いが難しい場合は、家庭裁判所に「夫婦関係調整調停(離婚)」を申し立てることになります(なお、離婚の成立後であれば、「財産分与請求調停」となります。)。調停では、調停委員が間に入り、双方の意見を聞きながら、公平な解決を目指して話し合いを進めます。 **注意点として、この申立ては離婚した時から2年以内に行う必要があります。**この期間を過ぎてしまうと、原則として財産分与を請求できなくなるため、注意が必要です。
審判・裁判の流れ
財産分与請求調停において合意が成立しない場合、調停手続きは「審判」という手続きに移行します。審判では、裁判官が双方の主張や提出された資料など、一切の事情を考慮して、分与の額や方法を決定します。
また、夫婦関係調整調停(離婚)において合意が成立しない場合、調停は不成立となりますが、この場合、離婚するためには、裁判を行わなければなりません。
離婚そのものを裁判で争う(離婚訴訟)場合には、その訴訟手続きの中で財産分与の申立てを行うことができ、離婚の判断とあわせて財産分与についての判断が下されます。
手続きを進める上での注意点
最後に、手続きを進める上での注意点を解説します。
慰謝料との違い
財産分与と慰謝料は、法的な性質が異なります。
- 財産分与: 夫婦で築いた財産を清算することが主な目的です。離婚の原因を作った側(有責配偶者)からでも請求できます。
- 慰謝料: 不貞行為やDVなど、離婚の原因を作った相手の行為によって受けた精神的苦痛に対する損害賠償です。
ただし、財産分与の金額を決める際に、慰謝料的な要素を含めて上乗せすることもあります。
なお、財産分与と慰謝料は、請求できる期間も異なります。財産分与は離婚後2年以内(民法第768条第2項但書)、離婚の成立そのものによって生じた精神的苦痛を慰謝するための慰謝料は原則として離婚後3年以内(民法第724条)に請求しなければなりません。
財産隠しの防止
離婚協議を有利に進めるために、相手が財産を隠してしまうケースもあります。そうした事態を防ぐためにも、相手名義の財産について、情報を集めておくことが重要です。
まとめ
離婚は人生の大きな節目です。財産分与は、その後の生活を支える重要な要素となりますので、基本的な知識をしっかりと身につけ、悔いのない再スタートを切れるように準備を進めましょう。
※本コラムは掲載日時点の法令等に基づいて執筆しております。
- 2026.02.02
財産分与とは?やさしい解説ガイド - 2026.01.26
財産分与の進め方|協議・調停・審判・裁判の違いと実務上の留意点 - 2026.01.19
財産分与における借金の取り扱い