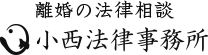退職金の財産分与~財産分与において退職金の計算方法と支払時期が問題となった事例(広島高判平成19・4・17)
- 財産分与
退職金は賃金の後払い的性格を有することから、財産分与の対象とするべきという考え方が一般的です。
本コラムでは、財産分与において退職金の計算方法と支払時期が問題となった事例(広島高判平成19・4・17)を紹介いたします。
争点
退職金が財産分与の対象となる場合の計算方法および支払時期
裁判所の判断
一審被告Y1が将来定年により受給する退職手当額は、一審被告Y1が定年まで勤続することを前提として初めて受給できるものである上、支給制限事由…に該当すれば退職手当を受給できず、また、退職の事由の如何によって受給できる退職手当の額には大きな差異がある…から、現時点において、その存否及び内容が確定しているとは言い難く、一審被告Y1の定年時における退職手当受給額を現存する積極財産として財産分与の対象とすることはできないものというべきである。
他方、一審被告Y1は、現時点において自己都合により退職した場合でも退職手当を受給できるところ、その額を証拠上認められる一審被告Y1の最近の給与月額を基礎として計算すると、勤続年数32年(昭和49年4月から当審口頭弁論終結日まで。1年未満の端数は切り捨てる。)の自己都合による退職の場合の支給率は43.75であるから、その額は1956万3600円(計算式:447、168円×43.75)となる。
そして、一審被告Y1が一審原告と婚姻した昭和49年×月×日から別居した平成14年8月×日までの約28年間、一審被告Y1が○○の職員として勤務したことについては、一審原告の妻としての協力があったことは明らかであるから、一審被告Y1が自己都合により退職した場合でも上記金額の退職手当を受給できる地位にあることは、それを実際に受給できるのが将来の退職時ではあるものの、これを現存する積極財産として財産分与の対象とするのが相当であり、上記金額のうち婚姻関係に基づく同居期間に対応する額である1711万8150円(計算式:19、563、600円÷32年×28年)の範囲で財産分与の対象になるものというべきである。
…本件において、一審原告の妻としての寄与割合は2分の1とみるべきところ、本件に顕れた諸般の事情並びに扶養的要素を考慮すれば、一審被告Y1が一審原告に対して支払うべき財産分与額は950万円とするのが相当である。
なお、一審被告Y1に対する退職手当は、退職時に支給されるものであるから、一審原告に対する上記退職手当に由来する財産分与金の支払いは、一審被告Y1が将来退職手当を受給したときとするのが相当である。
将来、退職手当の額が現在の水準よりも低くなる可能性があることは否定できないが、このような流動的な事情を考慮するのは相当とは思われず、上記判断を左右するに足りない。
よって、一審被告Y1は,一審原告に対し、離婚に伴う財産分与として、950万円を退職手当受給時に支払うべきである。
コメント
財産分与の際に、退職金の取扱いが問題となることが多いです。
将来支給される退職金については、分与対象となる退職金額の算定方法と財産分与の時期が問題となります。
この点、過去の裁判例を見ると、分与対象となる退職金額の算出方法としては大きく3つに分けることができます。
- 別居時に自己都合退職した場合の退職金相当額を分与の対象とする
- 定年退職時の退職金から、別居後労働分を差し引いた上、中間利息を控除して口頭弁論終結時の現価を算出して算定する
- 定年退職時の退職金から、別居後労働分を差し引くが、支払時期を退職時として中間利息は控除しない
①の方法について
別居時に自己都合退職した場合の額を算定するため、定年退職までの期間が比較的長期になる場合であっても、将来の退職金を財産分与の対象とすることができ、なおかつ定年退職まで分与を待つ必要がありません。
しかし、分与義務者に支払能力があることが必要となるため、将来の退職金以外に一定の預貯金等があることが前提となります。
②の方法について
定年退職時に受領する退職金額をベースに算定を行うため、別居時と定年退職時の時期が近い場合で、別居時に自己都合退職した場合と定年退職時の退職金の額に相当な開きがある場合に、分与を求める側に有利となります。
しかし、この方法もまた分与義務者に支払能力が求められる上、市中金利より高い金利で中間利息が控除されるため、実際に支払われる金額が低くなってしまう可能性があります。
③の方法について
退職時に支払うことになるため、離婚時に分与義務者に資力がない場合であっても分与対象としやすくなります。
一方、退職まで期間がある場合、将来給付の債務名義を取得した場合であっても、回収できなくなるリスクがあります。
上述の判例は、③の方法を採用したものになります。
※本コラムは掲載日時点の法令等に基づいて執筆しております。